
第1コリント:第12章(1–11節)
11月 11, 2025
著者:ピーター・アムステルダム
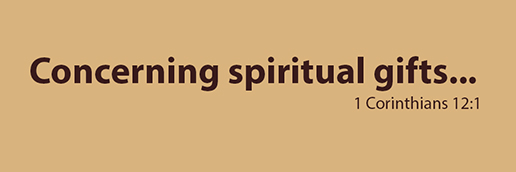
第1コリント:第12章(1–11節)
[1 Corinthians: Chapter 12 (verses 1–11)]
July 1, 2025
兄弟たちよ。霊の賜物については、次のことを知らずにいてもらいたくない (1コリント12:1)。
パウロが、コリントの信徒たちへの書簡のこの章を、「さて(聖書協会共同訳等)、… については」という言葉で始めているので、彼らから送られてきた手紙で提起されていた質問や問題に話を戻していることがわかります。この主題について書き始めるにあたり、パウロは、霊の賜物について知らずにいてもらいたくないと述べています。また、彼らを「兄弟たち」と呼ぶことで、家族的な雰囲気をつくり出しています。
あなたがたがまだ異邦人であった時、誘われるまま、物の言えない偶像のところに引かれて行ったことは、あなたがたの承知しているとおりである。そこで、あなたがたに言っておくが、神の霊によって語る者はだれも「イエスはのろわれよ」とは言わないし、また、聖霊によらなければ、だれも「イエスは主である」と言うことができない (1コリント12:2–3)。
パウロはこの2つの節で、コリントの信徒たちがまだ異邦人(異教徒)であり、惑わされて、物の言えない偶像に引かれて行ったときと、クリスチャンになって、神の霊によって語るようになった経験とを、対比しています。一部の解釈者は、パウロが対比しているのは、異教徒は偶像に導かれ、クリスチャンは聖霊に導かれるという点であると考えています。また別の解釈では、異教における恍惚状態で話をする経験と、教会における聖霊の超自然的な働き(特に異言と預言に関して)とを対比していると考えられています。
コリントの信徒の中には、異教の礼拝に関わったことがあるため、これらの賜物について懸念を抱く者がいたのかもしれません。パウロは彼らに、御霊に満たされた人の口は「イエスは主である」(1コリント12:3)と告白するのだと、保証しています。
霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。務は種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる神は、同じである (1コリント12:4–6)。
これらの節でパウロは、御霊と主と神という、三位一体の3つの位格すべてに言及しています。パウロはコリントの信徒たちに、すべての信者に与えられる賜物について説明をしようとしており、そうするにあたり、その賜物の源は、「すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる」三位一体の神ご自身であることを明確にしています。
パウロはまず、「霊の賜物は種々あるが、御霊は同じ」であり、それぞれが教会で異なる目的を果たしていると述べています。パウロの要点は、聖霊はただおひとりであり、その方がキリストを信じるすべての人の内に宿っておられるということです。御霊が、一部の信者にのみ与えられ、他の信者には与えられない、ということはありません(ローマ8:9)。信者は皆救われており、神の御霊がその内に宿っておられます。霊の賜物はさまざまでも、それらはすべて聖霊から来ているのです。
さらにパウロは、「務は種々あるが、主は同じである」と付け加えています。「務め」と訳されているギリシャ語は、「奉仕」とも訳されることがあります。パウロは、信徒たちのさまざまな奉仕や務めや活動の中に、同じ主が働いておられるのだと指摘しています。彼はコリントの教会に、神が彼らにさまざまな賜物と務めを与えてくださったのは、一致を築くためだと理解してほしいのです。
各自が御霊の現れを賜わっているのは、全体の益になるためである (1コリント12:7)。
ここでパウロは、まず、神は各信者に御霊の現れをお与えになると述べてから、一致、多様性、配分という主題について説明していきます。聖霊が内住している信者には、概して、その人生において御霊の臨在が何らかのかたちで現れるものです。パウロは、各信者に御霊の現れがあるのは「全体の益になるため」だと述べることで、一致を強調しています。ある人が書いているように、「霊の賜物は常に、それが用いられるために与えられるのであり、しかも、その賜物を有している個人ではなく、信者の集まり全体を造り上げるために使われるべきです。」[1]
御霊によって与えられる霊の賜物はすべて、キリストの体に属する他者に仕えるためのものです。霊の賜物のどれ一つとして、それを賜わった本人だけに益となり、役立つように与えられてはいません。
すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、ほかの人には、同じ御霊によって知識の言、またほかの人には、同じ御霊によって信仰、またほかの人には、一つの御霊によっていやしの賜物、またほかの人には力あるわざ[奇跡を行う力(聖書協会共同訳)]、またほかの人には預言、またほかの人には霊を見わける力、またほかの人には種々の異言、またほかの人には異言を解く力が、与えられている (1コリント12:8–10)。
パウロはここで、クリスチャンの人生における霊の賜物の現れの例をいくつか挙げています。そうするにあたり、御霊に4回言及することによって、これらの賜物が神から、すなわち聖霊から来ることをコリントの信徒たちに思い起こさせています。
新約聖書に記された、御霊の現れの他のリストと比較してみると、このリストはおそらく、コリント教会に現れている御霊の働きとしてパウロが知っていたものを、霊の賜物のいくつかの例として挙げたに過ぎないことがわかります。たとえば、ローマ12章6–8節にあるリストには、奉仕、教え、勧め、分け与え(施し・寄付)、指導といった他の賜物が含まれています。また、エペソ4章11–12節には、伝道や牧会といった、「聖徒たちをととのえて奉仕のわざをさせ、キリストのからだを建てさせ」るために与えられた他の賜物が記されています。
パウロはコリントの信徒たちへの手紙で、霊の賜物の現れを9つ、簡潔に挙げています。いくつかの賜物がどのように現れるかについては、詳細がほとんど記されておらず、歴史を通して、聖書学者たちはさまざまな解釈を提示してきました。その内、3つの賜物(知恵の言葉、知識の言葉、霊を見わける力)については、新約聖書で言及されているのはこの箇所だけです。
以下は、これらの賜物それぞれの概要です。(それぞれの賜物について、より詳しく知りたい場合は、『そのすべての核心にあるもの』シリーズの「御霊の賜物」パート1とパート2を参照してください。)
- 知恵。コリント人の中には、その時代の知恵を誇る者もいましたが、パウロは自らの教えの中で、世の知恵を退け、真の知恵はキリストの救いの御業にこそ見いだされると宣言しています。(1コリント2:1–5)。このような知恵は、導きと助言をもたらす聖書の真理を、信者が日常生活に適用するのを助けます。
- 知識。「知識の言葉」が何を指すかについては、いくつかの解釈があります。聖書学者たちは、一つ前の知恵の賜物と同様に、これはおそらくイエスと福音における神の救いの計画に関する知識を指しているのだろうとしています。学者の中には、パウロが知識を奥義(神秘)や啓示、預言と結びつけることがあるので(1コリント13:2; 14:6)、ここで彼が書いているのは、霊的真理や奥義についての超自然的な知識と理解のことであると考える人たちもいます。
- 信仰。信仰の賜物は、人に救いをもたらす信仰、すなわち、すべてのクリスチャンが持っているイエスへの信仰を指すものではありません。それよりも、イエスが「からし種一粒ほどの信仰」と表現された、山をも動かすことのできる類いの信仰を指しているようです(マタイ17:20)。信仰の賜物は、特定の状況において神がある方法で働かれるという強い確信、あるいは、特定の務めを成し遂げるために与えられる特別な信仰と理解できます。
- 癒やしの賜物。これは、イエスと初代教会の働きに見られる、病人の超自然的な癒やしを指しています。肉体の癒やしは、終わりの日に起こる体の復活の前味でした(マタイ8:17)。ここでの「賜物」が複数形になっていることは、この御霊の現れは時と場合によって、異なるかたちで起こることを示しているのかもしれません。この世において、すべての信者に癒やしが約束されているわけではありませんが、神の癒やしの賜物は、いずれ行われる体の贖いと、あらゆる病の癒やしを待ち望ませるものとして、与えられています(ローマ8:23)。
- 力あるわざ(奇跡を行う力)。この言葉は総称として、癒やしに限らず、さまざまな種類の奇跡を行う力を指しているものと考えられます(ヘブル2:3–4)。奇跡とは、神の超自然的な介入によって起こる、通常の自然法則を超える出来事のことです。聖書全体を通して、神は奇跡によって、ご自身とその性質や計画を現してこられました。四福音書すべてから、奇跡がイエスの宣教において重要な役割を果たしたことがわかります。この賜物が9つの賜物の中で5番目の位置に記されているという点は、他のあまり目立たない御霊の働き以上に強調されたり重視されたりすべきではないことを示唆しています。
- 預言。預言の賜物とは、信者が聞き手に対して、神のメッセージを伝える霊感された言葉を語るよう、御霊から与えられる力です。[2] 旧約聖書には、神の霊感のもとで、聖書の言葉と同等の権威をもって、神の言葉を語る預言者たちがいました。新約聖書において、預言の賜物は、神が心に置いたり、思い浮かべさせたりしたことをクリスチャンが他者に伝えることを指すことが多く、その権威は聖書と同等とはみなされませんでした。[3] パウロは教会に対して、預言を「吟味(検討)」し、「良いものを大事に」守るよう勧めています(1コリント14:29; 1テサロニケ5:19–21)。預言の賜物は、共同体を造り上げ、励まし、慰めるのに有益であるため、パウロは奨励していました(1コリント14:1–3)。
- 霊を見わける力。旧約時代のイスラエルでは、偽預言者や偽教師の本性を見抜かなければならないことがありました(申命記18:20–22)。新約聖書に記されているように、教会内でも、その始まりからずっと、同じことが起こっていました。「しかし、民の間に、にせ預言者が起ったことがあるが、それと同じく、あなたがたの間にも、にせ教師が現れるであろう。彼らは、滅びに至らせる異端をひそかに持ち込み、自分たちをあがなって下さった主を否定して、すみやかな滅亡を自分の身に招いている」(2ペテロ2:1)。「真理の霊」と「迷いの霊」を見わける力は、非常に貴重な賜物だったのです(1ヨハネ4:1–6)。
- 異言。異言の賜物とは、人が自分の知らない言語で語ることを指しており、その最初の現れは、五旬節の日に弟子たちに起こったことです(使徒2:4–11)。この賜物は、キリスト教会の歴史において、いくぶん意見の分かれるものでした。特に、それは人間の言語が、その言語を知らない人によって語られていたのか、あるいは、人間には知られていない言葉だったのか、という点です。パウロは、この賜物の異なる形態のものを異言とみなす余地を与えるために、意図的に「種々の異言」という曖昧さの残る表現を用いたようです。
- 異言を解く(解き明かす)力。「解く」と訳された言葉は、「翻訳する」とも訳せるものです。異言を解き明かす力は、語られた異言の種類によって、異なっていたと思われます。しかし、たとえ既知の人間の言語が話された場合でも、この賜物は、翻訳者が自分の知っている言語を訳す通常の能力を超えたものであり、自分の知らない言語を訳すという超自然的な力として理解されていたようです。パウロは後に、礼拝において異言が語られた場合、皆がそこから益を得られるよう、可能な限りそれを解き明かすべきだと教えています(1コリント14:2–5)。
すべてこれらのものは、一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままに、それらを各自に分け与えられるのである (1コリント12:11)。
こうして、御霊のさまざまな賜物の簡潔なリストを示した後、パウロは、すべての霊の賜物は同一の御霊の働きであると総括して、締めくくっています。これらの賜物が教会にとって重要なのは、聖霊によって授けられた力だからです。教会の各信徒は、それぞれ異なる賜物をいただいていますが、それは、個々の資質や状況の違いによってではなく、ただ一つの基準、すなわち、御霊の御心によって定められるのです(1コリント12:11)。
(続く)
注:
聖書の言葉は、特に明記されていない場合、日本聖書協会の口語訳聖書から引用されています。
1 Leon Morris, 1 Corinthians: An Introduction and Commentary, vol. 7, Tyndale New Testament Commentaries (InterVarsity Press, 1985), 167.
2 Morris, 1 Corinthians, 169.
3 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Bible Doctrine (Zondervan, 1994), 1052–1055.
